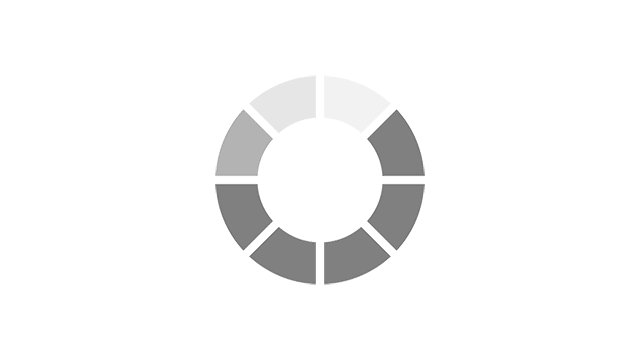
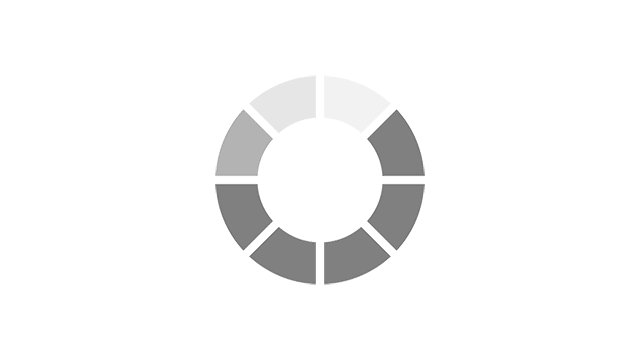
アステラスは、グローバルライフサイエンス企業として社会的責任を果たしながら、事業活動を行っています。革新的で信頼性の高い医薬品を提供することにより、世界中の人々の健康に貢献することを目指しています。当社は、研究・開発から製品に関する情報提供までの全ての事業活動において人権を尊重するとともに、関連法規の遵守に努めています。
アステラスがサプライチェーン全体で環境および社会的責任を果たすためには、コンプライアンスを遵守しつつ環境・社会・ガバナンスの方針を私たちのプロセスや意思決定に取り込むことが重要と考えています。この目標を達成すべく、アステラスはサステナビリティ向上に向けた私たちの責任および取引先に期待する責任を5つの柱で示したThe Sustainable Procurement Pledge/持続可能な調達宣言を定めています。また、グローバルで持続可能な調達の取り組みを実行し、事業活動の健全なネットワークの構築を目指します。
アステラスビジネス」パートナー行動規範
アステラスは、取引先に対し、アステラスと取引先が事業を展開する国で適用されるすべての法律および規制を満たしまたはそれを超えることを期待します。私たちは、取引先が法令遵守にとどまらず、関連する国際基準を満たし継続的な改善に努めることでより高いレベルでの法的遵守を奨励しています。
ビジネスパートナー行動規範に規定された基準は、特定の契約上の要件を変更または置き換えることを目的としたものではありません。むしろこの行動規範は、アステラスが取引先に期待するビジネス行動の基本原則を定めています。取引先がこの行動規範よりも厳格または詳細な要件に同意した場合、私たちは取引先がそれらの契約条項を遵守することを期待します。現在、アステラス ビジネスパートナー行動規範は、5つの柱の1つとして持続可能な調達宣言の不可欠な要素となっています。
取引先に対する調達活動基本方針
アステラスの購買担当者は、公平・公正で透明性の高い調達活動を行うために、自らを律する規範として「取引先に対する調達活動基本方針」を遵守し、行動することが求められています。
重要な取引先を対象とするリスク評価
取引先の中でも特にアステラスの事業継続への影響が大きい「重要な取引先(significant business partners)*」については、その選定プロセスにサステナビリティ・リスク評価を組み込み、グローバルで評価を実施しています。サステナビリティ・リスク評価は、(1)質問票に対する取引先の回答、(2)外部データベースの情報、(3)人権、環境、安全衛生、個人情報保護など持続可能性に関わるリスクに精通した社内の専門家による評価を基本とし、必要に応じて(4)アステラス社員が現地を訪問して行う実地調査の結果を組み合わせてリスクレベルを判断しています。環境、安全衛生に関するリスク評価については、PSCI(Pharmaceutical Supply Chain Initiative)が公開している質問票(SAQ)の内容にアステラスのオリジナルの質問も加えて評価を実施しています。また、取引内容によっては再委託先までサステナビリティ評価も実施しています。
サステナビリティ・リスク評価は、2019年2月より日本、北米、欧州で運用開始され、現在では南米やアジア各国でも導入されています。グローバルで共通のプラットフォームを活用することで評価結果やプロセスを一元的に管理しています。アステラスは、第三者間の取引に応じて、業務委託先に対してサステナビリティ評価を実施する場合があります。
アステラスでは、取引先選定の段階で改善可能なリスクを特定した場合は、取引先に対して改善を働きかけ、経過をモニタリングしています。なお、重大なリスクを特定し、かつ改善が難しいと判断した場合は取引を行いません。
また、取引開始後も、ビジネス部門がリスクの状況を継続的にモニタリングしているほか、2年ごとに持続可能性に関わるリスクレベルを質問票で再評価しています。さらに、必要に応じて2年以内であっても再評価を実施しています。
*原料の仕入先(直接材、間接材を問わず)や業務委託先、医薬品卸売業、販売提携先を含むアステラスの事業継続に対する影響が大きいと判断した取引先
取引先の実地監査
2020年には、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による移動制限がありました。状況を勘案したうえで、アステラスは、排水処理施設の運用状況、従業員の作業環境、化学物質曝露防止の取り組みなどについて、日本国内で2社の企業に対し実地調査を行いました。指摘事項があった場合、アステラスは改善案を提示して是正計画の策定を求めており、現在は策定された是正措置計画に基づいてその改善状況を追跡しています。
取引先のダイバーシティ
「変化する医療の最先端に立ち、科学の進歩を患者さんの価値に変える」というアステラスのVISIONにおいて、人種、国籍、性別、年齢に関係なく、多様な個人や企業が重要な役割を果たすことを確かなものにするため、アステラスは、ダイバーシティインクルージョンへの取り組みの一環として、取引先のダイバーシティを推進しています。私たちは、多様な取引先がそれぞれの経歴や経験により、私たちの価値エコシステムへ重要な貢献をしていると考えています。
アステラスは、日本の下請法を遵守しており、またアメリカ合衆国退役軍人省によって確立されたガイドラインに準拠して米国中小企業プログラムを長年にわたり実施しております。アステラスの米国中小企業プログラムは、経営不振の企業、女性が経営する企業、退役軍人所有企業、傷痍退役軍人所有企業、歴史的低開発地域の企業など、多くの不利な立場にある中小企業へ取引の機会を提供することに重点を置いています。
アステラスのサステナビリティとポリシーに従い、私たちは潜在的な取引先と考えられる全ての企業に公正かつ公平な機会を提供し、アステラスの多様性への取り組みを拡大し、アステラスのサプライヤーダイバーシティプログラムを実施しています。このプログラムは、従来は除外されていた幅広いサプライヤーグループを対象とし、これらの取引先に成長と発展の機会を創出することを目的としています。このプログラムは、当初は米国に焦点を当て、今後数年間で他の国にも拡大する予定です。
The Astellas Supplier Diversity Program includes suppliers that fall under one or more of the following categories:
当社のサプライヤーダイバーシティプログラムは、エンゲージメント、ダイバーシティ&インクルージョンの使命に沿ってアステラスグローバル調達によって管理されており、アステラスの調達プロセスに組み込まれています。アステラス製薬の今後の機会をご希望の場合は、こちらまでご連絡 ださい。
アステラスでは各種関連法規遵守および倫理的配慮を行い、革新的な医薬品と医療ソリューションを創出のため研究活動に取り組んでいます。
人を対象とする研究における倫理的配慮
アステラスでは、ヘルシンキ宣言*1および各国で定められた法令や指針などに則り、適切に研究参加者の同意を得て、人を対象とする研究や、ヒトに由来する試料や情報を用いた研究を実施しています。
日本では、研究を実施する社員を対象に生命倫理やゲノム研究、臨床研究に関する研修を行い、研究参加者の人権の尊重や個人情報の保護などに努めています。また、社外有識者を含む医学系研究倫理審査委員会を設置し、倫理的および科学的な観点から研究計画について公正かつ公平に審査しています。同委員会については、厚生労働省の倫理審査委員会報告システム*2で公表しています。
*1ヘルシンキ宣言:ヒトを対象とする医学研究に関わる医師やその他の関係者に対する指針を示す倫理的原則。
*2詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。https://rinri.mhlw.go.jp/
幹細胞の研究開発における倫理的配慮
アステラスは、これまで治療手段の無かった疾患に対して新たな治療手段を提供していくために、幹細胞*3を利用した研究開発を積極的に推進しています。
一方で、ヒト幹細胞を用いた研究の推進にあたっては、慎重に検討すべき懸念点が生じ得ることも認識しています。特に、ヒト胚性幹細胞(ES細胞)を用いた研究は、社会的・生命倫理的な課題に十分配慮する必要があります。
こうした考え方や認識に基づき、アステラスは、ヒト幹細胞を用いた研究開発において遵守すべき基本的な事項を「幹細胞の研究開発に関するポリシー*4」に定めています。具体的には、ヒト幹細胞に関するすべての研究開発活動において、研究開発を行う国や地域の関連法令や規制を遵守しています。また、社内責任者および社外専門家で構成する委員会を設置し、研究開発活動の倫理性、科学的妥当性および研究の正当性について監督・助言を受けることとしており、すべての研究開発プログラムは同委員会による倫理面・科学面の審査を経て実施しています。さらに、ヒト胚性幹細胞を樹立・利用する場合は、米国科学アカデミーによるガイドラインなど、世界の主要な科学的権威によって制定された倫理基準を満たしたうえで行っています。
*3幹細胞:自己複製能と多分化能を持った細胞。
*4詳細は以下のウェブサイトをご参照ください
Policy and Positioning Hub Policy on Stem Cell Research and Development
ヒトゲノム編集における倫理的配慮
アステラスは、「先端・信頼の医薬で世界の人々の健康に貢献する」を経営理念に掲げるライフサイエンス分野のリーディングカンパニーとして、ヒトゲノム編集技術の最先端にいます。世界中に拠点を置くアステラスの社員およびパートナーは、大学等の学術研究機関やバイオテクノロジー企業との連携のもと、疾患生物学への深い理解と、ゲノム編集/ゲノム制御等を含む最先端の技術プラットフォームや治療モダリティを組み合わせることにより、革新的な治療法を開発しています。
アステラスは、ヒトゲノム編集における管理や監視体制に関する国際基準の策定を検討している、米国国立標準技術研究所(NIST)ゲノム編集コンソーシアム、欧州科学アカデミー諮問委員会(EASAC)、米国薬局方、国際標準化機構(ISO)、世界保健機関(WHO)、およびその他の国際機関の考え方を支持しています。また、体細胞や生殖細胞にゲノム編集技術を用いる基礎研究および前臨床研究は、患者さんの健康と福祉に貢献するために適切な法的、倫理的規則と監視のもとに実施されるべきであると考えます。臨床利用段階においても、関連する法律や指針を遵守し、適切かつ科学的な目的で研究開発を実施します。このような、アステラスの「ヒトゲノム編集に関する基本的な考え方」は会社ウェブサイトで公開しています*5。
*5 詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。
Policy and Positioning Hub Position on Human Genome Editing
動物実験における倫理的配慮
アステラスは、動物の愛護及び管理に関する法律など動物に関する各種関連法およびガイドラインを基に作成した「動物の管理および使用に関するポリシー*6」に基づいて動物実験を行っています。社外有識者を含む動物実験委員会を設置し、4Rの原則*7を確認し動物実験実施の可否を審査しています。また、アステラスの動物実験施設は、AAALAC*8認証を取得する事により、透明性の確保に努めています。
*6詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。
Policy and Positioning Hub Policy on Animal Care and Use
*74Rの原則:Replacement(代替法選択の可能性の検討)、Reduction(使用数の削減)、Refinement(苦痛の排除)、Responsibility(科学的、倫理的な正当性の検証責任)。
*8AAALACインターナショナル:国際実験動物管理公認協会。動物管理および使用プログラムに対する国際的認証を提供する団体で、動物実験が科学的・倫理的に実施されているかを調査・認証する機関。
バイオテクノロジー、バイオハザードへの対応
アステラスは、世界保健機関(WHO)実験室バイオセーフティ指針*9、米国疾病予防センター(CDC)バイオセーフティマニュアル*10、米国国立衛生研究所(NIH)ガイドライン*11および各国の法律等に準拠して、遺伝子組換え生物の取り扱いや感染性材料を使用する実験を行っています。
*9Laboratory Biosafety Manual 4th Edition
*10Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 6th Edition
*11NIH Guidelines for Research Involving Recombinant or Synthetic Nucleic Acid Molecules
生物多様性への配慮
アステラスは「遺伝資源についての基本的考え方*12」のもと、生物多様性条約*13の考え方に沿ってその多様性の保全に配慮し、新たな遺伝子改変技術の利用に関しては、環境や人の健康にもたらす影響に配慮しながら慎重に取り扱っています。また生物多様性条約に関連する名古屋議定書*14の遺伝資源の利用とその利益配分に関する指針等に則り、遺伝資源の入手に際しては提供国の関係法令を遵守し、その利用によって生じる利益は公正に配分することとしています。
*12詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください:
Policy and Positioning Hub Position on Genetic Resources
*13生物多様性条約:生物多様性の持続可能な利用及び保全に関する国際条約
*14名古屋議定書:遺伝資源へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な分配に関する議定書
知的財産の取り扱い
知的財産の適切な保護は、競争力を維持しながら満たされない医療ニーズに対応していくために重要であり、アステラスは「知的財産に関するポリシー*15」を定めています。さらに、アステラスはイノベーションへの強いコミットメントを確認するとともに、知的財産権取り扱いの中心に患者さんのニーズを据えることを約束する「知的財産に関する10の主要原則からなる宣言 (IP PACT)*16」に賛同しています。
また、保健医療へのアクセス改善に配慮し、各国の医薬品調達部門がアステラスの医薬品特許情報に容易にアクセスできるよう、世界知的所有権機関(WIPO)が運営するThe Patent Information Initiative for Medicines(Pat-INFORMED)に参加し、イクスタンジ®、レキスキャン、ゴナックス®、スーグラ®、タルセバおよびゾスパタ®の特許情報をPat-INFORMEDのデータベースに掲載しています。
なお、アステラスは、国連が定めるLeast Developed Countries(LDCs)および世界銀行が定めるLow Income Countries(LICs)においては特許出願および特許権の行使を行いません。また、保健衛生の課題は製薬産業を含む多様な関係者が共有する責務であると認識しています。そのため、その他の途上国においても、差し迫った保健衛生の課題に対処するために、個別の事案に応じて柔軟に特許権のライセンスを検討しています*17。
*15詳細は、以下のウェブサイトをご参照ください。
Policy and Positioning Hub Policy on Intellectual Property
*16詳細は、以下のウェブサイトをご参照ください。
https://www.interpat.org/ip-pact/
*17詳細は、以下のウェブサイトをご参照ください。
Policy and Positioning Hub Position on Intellectual Property in Developing Countries
アステラスは、ヘルシンキ宣言および医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)などの関連法規制に則って、臨床試験参加者の人権や個人情報の保護に十分配慮し、新しい薬や治療法の候補の有効性・安全性を確認する臨床試験を実施しています。また、臨床試験の実施計画書は社内外の審査委員会で倫理的・科学的妥当性の観点から審査を受け、承認を得ています。
臨床試験の実施にあたっては、臨床試験参加者が試験の目的や方法、予測される利益と不利益、健康被害補償に関する事項などに関する説明を十分に受け、同意したうえで試験に参加していることを確認しています。さらに、臨床試験に関わる社員などへの教育・研修を定期的に実施するとともに、治験実施医療機関に対してモニタリングを行い、臨床試験がGCPに則って適切に実施されていることを確認しています。
また、臨床試験データを適切に管理し、臨床試験参加者のプライバシーと機密事項の保護に努めています。なお、外部委託している臨床試験においても同様の基準で実施されていることを定期的に確認しています。
臨床試験情報および試験結果の開示
アステラスは、臨床試験データの開示を進め、透明性を高めることに取り組んでいます。臨床試験データの価値を最大化し、そのデータを科学の進歩やイノベーションの推進に役立てるには、研究者をはじめ臨床試験データを活用する可能性のある方々が、臨床試験データに適切にアクセスできる必要があります。このようなアステラスの考えは「臨床試験データの開示に関するポリシー*1」としてコーポレートウェブサイト上で公開しています。
アステラスは、臨床試験を公的データベースに登録し、その臨床試験情報および試験結果を公開しています。第三者の専門家により構成される審査委員会が科学的有用性や研究者としての適格性などを審査して承認した場合には、各種関連する法律および規制に従い匿名化した患者レベルの試験データを、外部のウェブサイト*2を通じて、希望する科学者や医療関係者へ提供しています。また、アステラスの臨床試験結果ウェブサイト*3では、第I相から第IV相の介入試験の臨床試験結果の概要を、規制当局の承認取得後もしくは開発の中止後に公開し、医療関係者や一般の方が上記のウェブサイト上で確認できるようにしているほか、患者さんに対しては、医療関係者以外の方に向けた臨床試験結果の要約を提供しています。
*1詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
Policy and Positioning Hub - Policy on Disclosure of Clinical Trial Data
*2患者さんごとの試験データは以下のウェブサイトを通じて提供しています。
https://www.clinicalstudydatarequest.com/
*3以下のウェブサイトで臨床試験結果を提供しています。
www.clinicaltrials.astellas.com 及び/又は www.trialsummaries.com/Home/LandingPage
開発中の治療法への早期アクセスと臨床試験後のアクセス
アステラスは、「開発中の治療法への早期アクセスと臨床試験後のアクセスについての基本的な考え方*4」において、臨床試験以外で患者さんに治験薬を提供する際の対応をまとめています。
重篤な疾患、生命を脅かす疾患に苦しむ患者さんの中には、現在ある治療法をすべて試みても効果がなく、また参加基準を満たさないため臨床試験で治験薬の投与を受けることもできず、臨床試験への参加以外の方法による治験薬の投与を求める患者さんがいます。このような場合に患者さんの担当医から受ける治験薬の拡大アクセスの要請に対し、アステラスは、その要請が治験薬を使用するための条件に合致するか否かを公正かつ中立に評価し、適切に早期アクセスを提供できるよう取り組みます。さらに、早期アクセスプログラムは、医薬品の臨床開発が進行中であり、承認取得が計画されている国で実施されます。また、早期アクセスの要請があった国の規制に従って手続きが行われます。承認された治療プロトコールに従うことを医師に求める早期アクセスプログラムは、必要に応じてClinicalTrials.gov、EU 臨床試験情報システムおよび/または地域の登録機関に登録されます。
アステラス製品へのリクエスト・プラットフォーム
アステラスは、革新的な治療薬を患者さんへ持続的に提供するため、製品ライフサイクルを通じてアクセスプログラムを実施しています。
医療従事者が患者さんに必要な治療法にアクセスできることは、アステラスにとっての最重要事項です。私たちのリクエスト・プラットフォームを利用することで、医療従事者が患者さんに代わってアステラス製品の提供を依頼することができます。
このリクエスト・プラットフォームは、医療従事者が製品提供の依頼をするための一元的な申請窓口です。
アステラス 製品へのリクエスト・プラットフォームは こちらをクリックしてください。
患者さんの声を活かした臨床開発
アステラスでは、新しい薬や治療法の開発におけるすべての段階で、患者さんの声を活かした臨床開発を進めています。患者さんや患者団体との連携により、患者さんとそのご家族・介護者のご意見をお聞きしています。
例えば:
これらの取り組みを通じて、患者さんやその介護者が臨床試験に参加しやすい環境を整え、科学的に意義があり、かつ患者さんにとって意味のある試験結果が得られるよう努めています。
アンチ・ドーピングへの取り組み
スポーツで問題となっているドーピングは、医薬品の乱用・誤用とつながりが深く、重篤な副作用を招く危険性があるだけでなく、不正な流通や偽造医薬品の温床となり得るという点で医薬品業界にとって重要な課題です。アステラスはドーピングに使用される可能性のある治験中の化合物を特定し、誤用防止に取り組んでいます。
2016年10月、ドーピング撲滅と公衆衛生の向上に貢献するため、アステラスは世界アンチ・ドーピング機構(WADA)と、スポーツにおけるドーピングを目的とした医薬品の誤用や乱用の防止に向けた国際的な連携に関する契約を締結しました*5。
ドーピングでは、市販されている医薬品だけでなく、まだそれほど知名度が高くない、あるいは検出が困難な開発段階の化合物が誤用・乱用されることが少なくありません。この問題に対処するWADAの取り組みを支援するため、アステラスは、ドーピングで乱用される恐れがあるアステラスが単独開発中の化合物を特定し、その検出方法の開発段階において、関連情報をWADAに提供するよう協力しています。さらに、アステラスは、乱用を避けるために、臨床試験期間中ドーピングで使用される恐れがある化合物の誤用のリスクを最小限に抑えることにも協力しています。
品質へのコミットメント
アステラスでは、品質へのこだわりは単なる規制要件ではなく、科学の進歩を患者さんの「価値」に変えるという私たちのコミットメントの基盤です。
当社は、イノベーションと品質は密接に関連していると信じており、次の基本原則に導かれて、当社が提供する治療を頼りにする方々の期待を上回ることに専念しています。
安定供給と品質管理
安全で有効な医薬品を確実に製造し、安定的に患者さんに提供することは、製薬メーカーであるアステラスにとって極めて重要です。そのため、医薬品の製造工程における製造管理、品質管理の基準(GMP)、および適正流通の基準(GDP)に合致した独自の基準を設定し、製造施設・設備のほか、原料の調達から保管、製造、さらに配送まで、一貫した高水準の品質管理を徹底しています。
また、安定供給の維持・強化に向けて、さまざまな製造設備に対し継続的な投資を行っています。2020年には、富山技術センターにおいて、治験用および商業用バイオ原薬をグローバル基準に則って製造・供給する施設であるバイオ原薬棟を竣工しました。さらに、臓器移植後の拒絶反応を抑制する免疫抑制剤プログラフ®の原薬製造施設として第3発酵棟の建設も開始しました。また、焼津技術センターにおいては、抗体製剤および、高い技術が要求される今後の新しいモダリティ製剤にも対応できる無菌製剤製造ラインの新設に着手しました。遺伝子治療の領域においては、米国カリフォルニア州サウスサンフランシスコと、ノースカロライナ州 サンフォードにプラント(2022年中にGMP操業開始予定)を設置し、アデノ随伴ウイルス(AAV)原薬、AAV製剤およびプラスミドの製造等のケイパビリティを強化し、遺伝子治療プログラムの研究から商業化まで自社で供給可能な体制の構築を進めています。細胞医療においては、2020年4月に米国マサチューセッツ州ウェストボロに新たな製造拠点を設置し、GMP細胞原薬および細胞製剤製造のケイパビリティを強化しています。これら最新鋭の自社製造施設の建設により、高品質の製品を今後も安定的に供給する、より強固な生産体制の構築を目指しています。
品質監査
アステラスでは、グループ内の事業所と社外の製造・流通事業者の品質保証体制を定期的に監査しています。監査の頻度と深度はリスク分析に基づいて決定しています。グループ内の事業所に対する監査は、現行の医薬品の製造工程における製造管理、品質管理の基準(cGMP)、または適正流通の基準(cGDP)を実践しているすべての組織を対象としています。製品ライフサイクルの全段階、サプライチェーン全体にわたって、方針書や手順書に従い、監査を実施しています。社外事業者への監査では、cGMP、cGDP、アステラスの要件の遵守状況を評価しており、新規・既存を問わず実施しています。
安定供給のためのサプライチェーンマネジメント体制
グローバル製品の増加やモダリティの多様化、パートナーシップ・サプライヤーとの連携の増加などにより、サプライチェーンはますます複雑化しています。こうした環境変化を踏まえ、アステラスは、世界各地域の需要予測や在庫情報、供給計画を一元的に管理する体制を構築し、原薬の製造から製品の供給まで、グローバルにサプライチェーンマネジメントを強化しています。
また、グローバル・ロジスティクス・ネットワークを構築し、コールドチェーンを含む製品に対する多様な要求にフレキシブルに対応する機能とケイパビリティを実現するとともに、輸出入を含むロジスティクスのコンプライアンスを推進し、安定供給体制を強化しています。
さらに、商用サプライチェーン機能について、環境変化に合わせてサプライチェーン・プロセスを継続的に進化させる機能を日本、オランダ、米国の3拠点に設置し、グローバル・オペレーションにおける管理体制の強化を推進しています。
安定供給のための共同物流
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)を継続的に改善し、自然災害の発生時に医療用医薬品の安定供給を維持・継続させることは、製薬会社にとって最も重要な使命の一つです。また、厚生労働省から日本版「医薬品の適正流通(GDP:Good Distribution Practice)ガイドライン」が発出されており、GDPに準拠した保管・輸送時における品質の確保がより厳格に求められています。一方で、国土交通省、経済産業省、農林水産省は、働き方改革やドライバー不足、CO2削減等の物流課題に対応するため、荷主が物流事業者と協力して改善・改革活動を実施し、持続可能な物流体制を構築する「ホワイト物流」を推進しています。
こうした物流を取り巻く環境変化の下、アステラスは武田薬品工業株式会社、武田テバファーマ株式会社、武田テバ薬品株式会社、日医工株式会社とともに、北海道において医療用医薬品を共同で保管・輸送する仕組みを構築しています。この仕組みによって、輸送効率と品質管理レベルの向上を図るとともに、医薬品の供給経路を分散し、大規模自然災害など緊急時においても製品を安定供給できるよう努めています。今後も業界内の医薬品販売物流の共同化・標準化を進めるべく、取り組みを続けています。
また、この北海道での取り組みはコスト面でも効果があり、新たな物流拠点の設立が可能になったほか、CO2排出量の削減による環境負荷の低減効果もあります。こうした点が評価され、平成30年に経済産業省のグリーン物流優良事業者表彰で、経済産業大臣表彰を受賞しています。
2021年より九州にも共同物流センターを追加し、国内4カ所での製品在庫管理および供給管理の体制が整いました。
安定供給のための責任ある製造への取り組み
患者さんが、アステラス製品へ継続的にアクセスするためには、医薬品の安定供給が必要です。安定供給を確保するためには、製造時の事故発生リスクを最小化する必要があります。医薬品の有効成分である原薬には、複数の化学反応によって合成されるものがあります。そのため、合成に用いられる使用原料や化学反応の中には、火災等を引き起こすリスクが多く潜んでいます。
アステラスでは、製造過程のリスク最小化のために、各原薬の製造の研究開発段階において、化学反応の制御不能による異常な反応や、静電気の放電により引き起こされる火災発生など、事故につながるリスク評価を実施しています。例えば、製造工程に用いる化学物質の分解開始温度や化学反応で生じる熱を確認しています。さらに、火災防止に繋がる適切な製造設備を設計しています。このようにして、患者さんに「価値」を届けるため、より安全な製造プロセスへの改良を続けています。
責任ある製造プロセスによる安定供給を確保するためのこれらの取り組みは、患者さんがアステラス製品を継続的に使用していただくためにとても重要です。
医療過誤の防止、医薬品の識別性向上
アステラスは、患者さんや医療従事者が医薬品を取り違えないよう、使用者の視点に立った製品の提供に努めています。カプセル剤・錠剤に製品名を直接表示しているほか、包装シート(PTPシート)を分割しても薬剤名や含量を識別しやすくするなど、医療過誤の防止に取り組んでいます。また、PTPシートの表示の見間違えを防止するため、一部の製品においてPTPシートに見やすい色と書体を採用し、視認性の向上を図っています。
服用回数に注意が必要な医薬品については、医療過誤防止の観点からブリスターカード包装*1も採用しています。例えば2019年に新発売したエベレンゾ®錠20mg、同50mg、同100mgは、週3回服用する製品であることから、3錠単位のブリスターカード包装とすることで飲み間違えを防止するとともに、用量に応じてサイズや色、表示デザインを変えることで取り違えの防止も図っています。
また、患者さんの服薬コンプライアンスや飲みやすさの向上の観点から、製剤の小型化や剤形の変更にも取り組んでいます。例えば2018年に新発売したイクスタンジ®錠40mg(直径10.1mm)、同80mg(長径17.2mm)は、従来のイクスタンジ®カプセル40mg(長径21mm)と比較してサイズが小さく、1回当たりの服用錠数を低減することも見込めるため、患者さんの服薬時の負担を軽減することが期待されています。
*1PTPシートの両面を紙で覆ってカード状にした包装形態。
製品パッケージへのユニバーサルデザインの導入
一部の製品パッケージにユニバーサルデザインを導入しています。例えば、4週に1回服用するボノテオ錠50mgのユニバーサルデザイン容器は、開封性に優れたパッケージを採用し、飲み忘れ防止のために服薬日の記載欄を設けるとともにカレンダー用のシールを添付しています。また、文字の読みやすさに配慮し、ユニバーサルデザインフォントを使用しています。
FDA査察
アステラスは、現行の医薬品適正製造基準(current GMP:Good Manufacturing Practice)に準拠した独自の品質基準を定め、各製造現場でこの基準を採用しています。
製品リコールの履歴
| 会計年度 | FDA査察数 |
警告書発行 |
Form483受領数*2 | Form483受領工場 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 | 該当なし | 1 | 高岡(日本) |
| 2015 | 4 | 該当なし | 2 | ノーマン(US)*1高岡(日本) |
| 2016 | 2 | 該当なし | 1 | 富山(日本) |
| 2017 | 2 | 該当なし | 1 | 富山(日本) |
| 2018 | 3 | 該当なし | 1 | 高岡(日本) |
| 2019 | 2 | 該当なし | 1 | 富山(日本) |
| 2020 | 2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 2021 | 0 | - | - | - |
| 2022 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | 1 | 焼津 (日本) |
| 2024 | 1 | - | - | 富山(日本) |
*1 米国ノーマン工場は2016年8月にAvara Norman Pharmaceutical Services, Inc.へ譲渡済み。
*2 Form 483:米国食品医薬品局(FDA)による査察の結果、指摘事項があった場合に、FDAはForm 483を発行し、連邦食品医薬品化粧品法および関連法の違反となる可能性を通知します
品質マニュアル
アステラスは、品質保証部門の機能や活動を「品質マニュアル」に規定しています。世界各国・地域の各組織は、このマニュアルに基づき、グローバル・地域・国のレベルで、品質保証のための体制や、関連するさまざまな業務の運用管理や手順などに関するガイドラインと標準操作手順書類を策定し、教育・研修プログラムを通して内容の理解・浸透を図っています。これらの文書類については、定期的に、また必要に応じて見直し、規制の変更や改訂などの外部環境の変化に迅速に対応しています。
これらの文書は、定期的なおかつ必要に応じて改訂されます。規制の変更や改正など、外部環境の変化に対しては、レギュラトリー・インテリジェンス体制の確立を通じて迅速に対応しています。
販社における品質保証体制の強化
アステラスでは、世界中の患者さんに均一で高品質な医薬品を確実に供給するため、強固な品質保証体制をグローバルに構築しています。この品質マネジメントシステムは、グローバルおよびグループ横断的な品質ポリシーと合致するものです。グローバルな品質保証体制の中には、アステラスの全販社における品質保証活動も組み込んでいます。品質を重視するアステラスの企業文化を強化すると同時に、最高水準の人材を育成する目的でも、世界各国の販社に対して継続的に支援しています。
国内外の製造委託先との協働による環境に配慮した製造への取り組み
アステラスでは医薬品を製造するにあたり、患者さんだけでなく、地域社会や自然と共生した持続可能な社会づくりを目指して、環境に配慮した医薬品の製造方法の開発に取り組んでいます。一般的に医薬品の有効成分である原薬を化学合成する際には、有機溶媒等の環境に負荷がかかる材料を使用します。そのため、製造方法による環境への影響を評価し、環境負荷を極小化するために必要な対策を講じています。
近年,国内に限らず海外の委託先とも製造方法の開発段階から協働する機会が増えてきたために、環境への影響の評価と環境負荷の低減についても協働を開始しました。具体的には、アステラス環境基準の共有、委託先の環境・安全衛生に関するポリシーと製造プロセスの理解、化学合成の際に発生するガスや廃液の処理方法の確認と精査、それらを基にした対策の立案などです。委託先にアステラスが求める環境基準を共有し協働することにより、十分な環境対策を備えた製造方法の開発に注力しています。
アステラスは、医薬品の品質や安定供給のみならず、国内外の環境に配慮した医薬品製造も追求し、患者さんの利益と地球規模での環境保全に貢献します。
地域社会との関わりおよび環境への配慮
持続可能な医薬品生産に向けて、アステラスは、製造事業所の近隣住民や地域コミュニティとの対話の機会を設け、アステラスの取り組みを積極的に開示することで、良好な関係の構築に取り組んでいます。
アイルランドのケリー工場内には自然保護エリアが存在し、地域に開放して遊歩道を整備し、エリア内に存在する動植物の説明を記載した看板を設置しています。
環境保護や安全衛生、エネルギー保護をテーマにしたカレンダーを作成するイベントを毎年開催しており、地域の12の学校から毎年1,000件以上の応募があります。
また、地域の学校と協力して科学技術の浸透のためのイベント開催や、四半期に一度、地域の生物多様性の情報を紹介するレターの発行・配布といった活動も行っています。他にも地元の種々な団体との交流やサポートを通して地域社会に貢献しています。
環境負荷軽減や持続可能性を考慮した医薬品生産は重要な取り組みとなっています。医薬品製造に必要なさまざまな基準の順守と同時に、環境に配慮した取り組みを行っており、2020年には SEAI*3から「Energy Team of the year」を受賞しました。
*3SEAI(Sustainable Energy Authority of Ireland):CO2排出抑制をサポートするアイルランド政府所属の団体。
各種法令・規則を遵守し、高い倫理観に基づいて行動する
製品の適正使用の推進
アステラスの医薬情報担当者(MR)は、医療従事者に製品の添付文書に基づく適正使用情報を提供することで、自社の医薬品が安全かつ効果的に使用されるように努めています。MRは高い倫理観に基づいて行動し、適用法令・規制、業界ルール、アステラスグループ行動規準を含む社内規程を厳重に遵守しながら、製品の情報提供を実施しています。
メディカル担当者(MSL)は、製品の安全かつ効果的な使用方法をはじめ製品について科学的根拠に基づいた情報交換を医療従事者との間で行うことで、医療従事者の製品についての理解を促し、製品の安全かつ有効な使用を推進しています。MSLは信頼性が高く、理解しやすく、公正かつ偏りがない医学的・科学的情報を提供しています。MSLは製品の販売促進につながる活動は行わず、各種規則などに準拠し、高い倫理観に基づいて行動しています。
問い合わせ対応
アステラスは、患者さんや医療従事者からの問い合わせに対して、信頼性が高く、公正かつ偏りがない医療情報を提供する責任があると考えています。この責任を果たすことによって、医薬品の適正使用を促進しています。
この認識のもと、世界の国々にメディカルインフォメーションセンターを開設し、さまざまな問い合わせに対応しています。主要なインフォメーションセンターでは、営業日でなくとも24時間体制で緊急の問い合わせに対応しています。
医療情報に関する問い合わせ対応に際してアステラスは、適切で一貫性のある正確な情報の提供を目指し、常に改善を続けています。その一環として、グローバルな医療情報システムを導入し、問い合わせおよび世界中のグループ会社から提供される回答の管理を行っています。これにより、問い合わせに対して簡潔、迅速かつ正確に回答するとともに、患者さんや医療従事者のニーズを分析し、製品のライフサイクルマネジメントに役立てています。
最近は新たに地域別の医療情報ウェブポータルを導入し、製品に関する情報を、より詳しくダイレクトな形で医療従事者へ提供しています。
偽造医薬品対策
正規の医薬品流通経路に偽造医薬品が混入することは、患者さんが有効な治療を受ける機会を失うだけでなく、重度の健康被害を引き起こす可能性があるため、世界的に深刻な問題となっています。
アステラスは「偽造医薬品対策についての基本的な考え方」を明確に定め 、ウェブサイト上で公表しています*1。
アステラスでは、品質保証部門、サプライチェーン管理部門など複数の関連部門のリーダーで構成する委員会を運営しているほか、製品に関わるセキュリティ・リスクを日常的に監視するプロダクト・セキュリティ部門を設置し、偽造医薬品対策を行っています。これらの委員会や部門は、世界中の市場でアステラスの製品に影響を及ぼす不審な活動を監視するとともに、偽造医薬品や、アステラスの製品に悪影響を及ぼし患者さんをリスクにさらす可能性がある医薬品の横流し、盗難などの不法行為への対策を実施しています。
また、アステラスは、現行の規制や薬事法の定めに従って実施している製品へのシリアルナンバーの付与にとどまらず、計画的に偽造防止対策を進めています。さらに、他の製薬企業と連携してさまざまな活動に定期的に参画し、偽造医薬品の流通防止に取り組んでいるほか、各国の行政や司法当局における偽造医薬品の取り締まり活動に対しても積極的に支援・協力しています。
*1詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
Policy and Positioning Hub Position on Counterfeit/Falsified Medicines
製品回収
アステラスは、製品の安全性や有効性、品質に問題が生じた場合に実施するリコール制度を整備しており、関連情報を迅速に医療機関や影響を受ける関係者に伝達し、該当製品の回収を実施しています。
製品リコールの履歴
| 年度 | リコール数 |
重度
(クラス I) |
中度 (クラス II) | 軽度 (クラス III) | 分類なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2015 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2016 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1* |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 0 | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
*当局主導のリコール
ファーマコヴィジランス(PV)システムの向上
アステラスは、ファーマコヴィジランス(PV)機能とその他関連部門、販社、およびライセンスパートナーとの連携強化を通じて、PVシステムの更なる向上に継続的に取り組んでいます。これにより、規制要件への対応はもとより、製品戦略の拡大への対応、信頼性の高い製品情報の提供と製品の適正使用の推進につなげています。
アステラスは、製品の安全性情報を広く収集する体制を構築しています。PV機能に密接に関わる従業員だけでなく販社を含めた全従業員と契約社員を対象にPVについての研修を毎年実施することで、適切かつ迅速に安全性情報を収集する体制を維持・強化しています。また、PV機能以外の部門が外部事業者へ業務を委託する場合は、必要に応じて業務委託契約に安全性情報の収集に関する要件を追加しています。
PV機能と他の部門との連携強化によって、大規模な医療データベースなどのリアルワールドデータを自社製品の安全性評価に活用し、リスクの最小化につなげる取り組みも進めています。さらに、安全性情報の監視、データベースへの取り込み、処理・報告、安全性シグナルの早期検出・解析に活用できる自動化技術や人工知能技術の探索・評価も継続して実施しており、安全性情報の管理体制も今後強化していきます。
これより先は、アステラス製薬のウェブサイトではなく、外部サイトになります。アステラスは外部サイトのコンテンツやサービスについて一切責任を負いません。
外部サイトへ移動しますか?