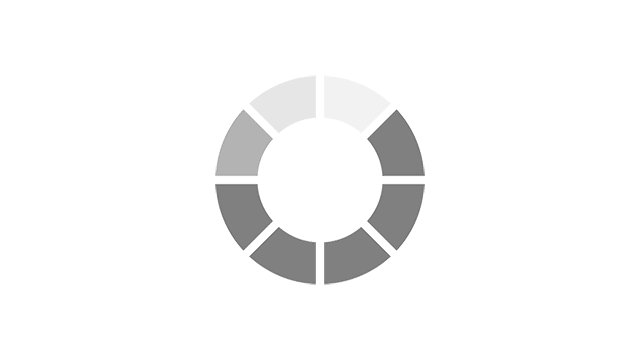
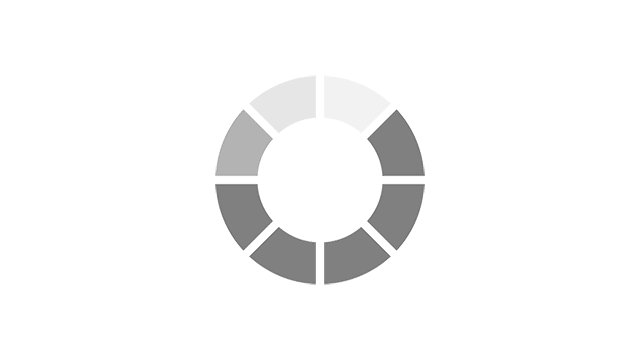
アステラスは、経営計画2021(CSP2021)の戦略目標4で示した通り、「サステナビリティ向上の取り組みを強化」することに全力を尽くしています。コアビジネスを通じて社会に貢献し、社会と企業のサステナビリティを高める、ポジティブなサイクルを創出することに重点を置いています。当社は、サステナビリティへの取り組みを導く、最重要課題および環境課題を複数特定しています。

代表取締役社長CEO
昨今、環境や経済の急激な変化により、社会の持続可能性(サステナビリティ)に対するステークホルダーの関心は益々高まっています。企業には事業を通じた前向きかつ積極的な社会貢献が期待されています。ヘルスケア分野においては、満たされない医療ニーズの高い疾患領域に社会からの要請がシフトし、次世代のモダリティ(治療手段)やデジタル技術の応用による革新的なヘルスケアソリューションが待ち望まれています。
アステラスは、「変化する医療の最先端に立ち、科学の進歩を患者さんの『価値』に変える」をVISIONに掲げ、革新的な新薬を始めとする様々なヘルスケアソリューションの創出により、患者さんの医療へのアクセスおよびアウトカム(成果や状況)の向上を目指しています。
アステラスが事業を通じて社会課題に取り組むことで、ステークホルダーから信頼され、アステラス自身の持続可能性が向上し、社会の持続可能性に一層貢献するという好循環が生まれます。それがアステラスの使命である "持続可能な企業価値の向上" の実現につながると考えています。
また、社会からの要請が高い、気候変動対策やその他の環境問題に対する取り組みを推進することで社会的責任を果たしていきます。
アステラスは、経営計画2021の戦略目標の一つとして「サステナビリティ向上の取り組み強化」を設定しており、サステナビリティを意識した経営を行っています。サステナビリティ活動を実施する上で指針となる「マテリアリティ・マトリックス」を作成し、社会とアステラスにとっての重要性の観点から、19の重要課題を特定しています。
その内、優先度の高い9つの最重要課題(マテリアリティ)を中心に全社一丸となって取り組みを行っています。
このような私たちのサステナビリティ向上への取り組みは、2つの観点で企業価値向上に繋がると考えています。
最先端の「価値」駆動型ライフサイエンス・イノベーターへの変革
社会には、有効な治療法が存在しない、もしくは既存の治療法では満足な結果が得られない病気に苦しむ患者さんやそのご家族がいらっしゃいます。アステラスは、単に疾患の症状を緩和する対症療法ではなく、細胞医療や遺伝子治療によって、疾患の根本的な原因に直接働きかけるといった新たな治療手段を提供する、革新的なヘルスケアソリューションの創出を追求しています。対症療法では、通院や入院によって患者さんご本人が負担を強いられるだけではなく、ご家族の看護や介護の負担も増えます。社会的、経済的損失は決して小さくありません。アステラスは、革新的な治療手段の創出に積極的に取り組むことにより、患者さんとそのご家族を長年の治療と介護から解放するとともに、わずかな治療回数により症状を大きく改善し、その結果、患者さんが普段の生活に早期に戻ることによって、地域のヘルスケアシステム全体の負荷を減らすことを目指します。
このように社会に大きな「価値」を生み出し、届けるための最たる原動力の一つが、イノベーションを生み出す組織文化であると考えています。アステラスの組織文化の醸成を図るとともに、イノベーション創出に寄与する人材の獲得・育成を通じて持続的な価値創造を実現し、アステラスが創出した「価値」を必要とする患者さんに広く届き渡るよう努め続けます。また、革新的な治療手段をはじめとするイノベーションを持続的に創出するためには、イノベーションに対する適切な価格設定が必要になります。アステラスは、患者さんやそのご家族、患者さんの健康を支える医療従事者を含めた社会に与える影響が、公正に価格へ反映されるための環境や仕組み作りにも取り組みます。
社会の期待に応える強靭かつ持続可能な事業活動の強化
私たちは、グローバルスタンダートで優れた品質の製品を製造し、安全性の高い製品を患者さんへ届け続けます。どのような状況であっても私たちの製品を安定的に患者さんへ届けることは私たちの使命です。調達・製造・流通に携わるすべての人々の人権や安全の保護を確保しつつ、サプライチェーン全体において外部環境の変化に柔軟に対応できる管理体制を構築していきます。加えて、その製品が患者さんに正しく適正に使用いただくための情報提供活動を継続します。常に病気で困っている患者さんやそのご家族を想い、患者さんにとって最適なヘルスケアソリューションは何か、アステラスの製品が患者さんに貢献できることは何かを考え、倫理的に活動を続けていく事で社会からの信頼を醸成していきます。情報提供活動のみならず、すべての事業活動において法令遵守と高い倫理観で活動を行い、公正な経営判断・運営を確実なものにするためのガバナンス体制を強化して、社会のサステナビリティに応えていきます。
社会のサステナビリティ向上への貢献は、アステラスのサステナビリティ向上に極めて重要である
私たちの使命を果たす、アステラスのサステナビリティ
アステラスは社会のサステナビリティの向上に貢献していくことが、事業を継続していく上で極めて重要であると考えます。具体的には、アンメットメディカルニーズ(満たされない医療ニーズ)に応えるヘルスケアソリューションを提供することや、事業活動において製薬会社としての社会的責任を果たすことにより、アステラスは社会のサステナビリティの向上に貢献しています。その結果、自社や自社の製品等に対する社会からの信頼が得られ、アステラスのサステナビリティを向上させると考えています。
このような好循環を生み出すことは、アステラスの存在意義である「先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献する」ことを通じた「企業価値の持続的向上」という私たちの使命を果たすことにつながります。すなわち、アステラスにとって、社会のサステナビリティの向上に貢献することは、経営理念の実践そのものです。
そのような考えのもとに行っている活動は、社外から高く評価されています。
一例として、アステラスは、投資の代表的指数の一つである「FTSE4Good Index Series」の構成銘柄に12年連続で選定されているほか、日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が採用するすべてのESG投資指数 (「FTSE Blossom Japan Index」「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」)の構成銘柄にも選定されています。

アステラスが取り組むサステナビリティには、「価値創造」と「価値保全」の2つの側面があります。
アステラスが事業活動を通じて、アンメットメディカルニーズ(満たされない医療ニーズ)という社会課題を解決することや、ステークホルダーの皆さまへの還元を行うことで、社会にとっての価値を創造しています。
一方、事業活動を通じて得た利益の再投資によって、アステラスは研究開発力を強化しています。また、各国政府、ビジネスパートナーから信頼を得ることで、新たな事業機会を生み出しています。すなわち、アステラスにとっての価値が創造されます。
アステラスは、環境負荷の低減、生物多様性の保全、コンプライアンスの徹底、腐敗防止などに取り組んでいます。これらの活動は、社会的価値に加え、レピュテーションリスクの軽減、企業ブランドの向上にも寄与し、企業価値を保全することにつながります。

コーポレートガバナンス体制に基づき、アステラスのサステナビリティに関する重要事項は代表取締役社長CEOが議長を務めるエクゼクティブ・コミッティ*1にて協議し、取締役会にて承認します。
また、サステナビリティの年度活動実績ならびに次年度活動計画は、業務執行の監督機能を果たす取締役会へ報告しています。長期的・戦略的かつ全社的な視点から各部門によるサステナビリティ向上のための活動を推進するため、推進体制としてサステナビリティ コミッティと 「環境・社会・ガバナンスワーキンググループ(E・S・Gワーキンググループ)」 を設置しています。
※1 アステラス製薬およびグループ会社における経営戦略、製品戦略、経営管理、人事等に関する重要事項を協議する機関
サステナビリティ コミッティでは機会やリスクを含め、業務執行に関わるアステラスの重要なサステナビリティ事項に関しての協議を行います。専門的かつ実行性を伴った議論を行うために、部門横断でファンクショナルユニット*2長レベルのメンバーで構成された組織であり、委員長およびメンバーは経営戦略担当役員(CStO:Chief Strategy Officer)によって任命されます。
*2 各トップマネジメントに直接レポートするビジ ネス遂行のための組織
E・S・Gワーキンググループは、案件ごとに部門横断のメンバーで構成され、外部の環境変化や各種原則・ガイドラインを参考にしながら、アステラスの環境・社会・ガバナンスの取り組むべき課題や機会の特定を行います。
また、関連部門と改善計画の立案と目標の設定、取り組みの進捗確認を実施します。
サステナビリティ コミッティを主管するファンクショナルユニットとしてE・S・Gワーキンググループの事務局業務を含めたグループ全体のサステナビリティ課題に対応し、活動全体を管理します。また、コミュニケーション機能と協働しながら社内外へアステラスのサステナビリティ活動を展開しています。

変化する社会に柔軟に対応し、アステラスならではの観点で課題に挑む
アステラスのサステナビリティ向上の取り組みは、企業価値を持続的に向上させることに繋がっています。社会および事業を取り巻く環境が著しく変化するなか、私たちは社会とアステラスの双方にとって重要な課題を特定し、優先順位を付け、サステナビリティの取り組みの羅針盤となるマテリアリティ・マトリックスを2021年度に改定しました。
新たなマテリアリティ・マトリックスでは、19の重要課題を選定し、うち9つを最重要課題(マテリアリティ)としました。このマテリアリティに最優先に取り組み、最先端の「価値」駆動型ライフサイエンス・イノベーターへの変革」、および「社会の期待に応える強靭で持続可能な事業活動の強化」を推進することで、社会とアステラス、双方のサステナビリティの向上を目指します。

SDGsや各種フレームワーク(国際統合報告フレームワーク、SASBスタンダード、GRIスタンダード、ISO26000、グローバル・コンパクトの10原則、TCFD提言)、ステークホルダーとのコミュニケーション、ESG調査の評価項目などを参考に、アステラスが取り組むべき重要課題を特定しています。
2021年度のマテリアリティ・マトリックスの更新では、前回の更新(2017年度)以降のサステナビリティの潮流変化に関する調査も実施し、経営計画2021との整合性、業界独自の課題を確認し、改めて19の重要課題を特定しました。
「社会にとっての重要性」と「アステラスにとっての重要性」の観点から、特定した社会課題に優先順位を付け、マテリアリティ・マトリックスを作成しました。
「社会にとっての重要性」では、国際機関・政府や、NGO、投資家、業界団体などグローバルでのステークホルダーの関心の高さや、社会課題による経済損失規模に基づいて重要度を検討しました。「アステラスにとっての重要性」では、リスクだけでなく、アステラスのケイパビリティやアセットにより課題解決に貢献できる機会の有無を含めて検討し、経営層インタビューによる経営の視点も加えて重要度を検討しました。
機関投資家、業界団体、NPO、NGOなど多様なステークホルダーから提供される情報や専門家へのインタビューにより内容を検証し、信頼性や客観性を担保しました。その後、社内の組織横断メンバーで構成される会議体(サステナビリティ コミッティ)での協議を経て、エグゼクティブ・コミッティ*における協議および取締役会での審議と承認がなされ、マテリアリティ・マトリクッスを最終化しました。
機関投資家、業界団体、NPO、NGOなど多様なステークホルダーから提供される情報や専門家へのインタビューにより内容を検証し、信頼性や客観性を担保しました。その後、社内の組織横断メンバーで構成される会議体(サステナビリティ コミッティ)での協議を経て、エグゼクティブ・コミッティ*における協議および取締役会での審議と承認がなされ、マテリアリティ・マトリクッスを最終化しました。
マテリアリティ・マトリックス更新の必要性については年1回サステナビリティ(ファンクショナルユニット)で確認しています。また、特定された最重要課題に対しては、取り組み目標と達成に向けたアクションプランを策定しています。
*アステラス製薬およびグループ会社における経営戦略、製品戦略、経営管理、人事等に関する重要事項を協議するコミッティ。
私たちは、特定した9つの最重要課題(マテリアリティ)に優先的に取り組むことで、「最先端の『価値』駆動型ライフサイエンス・イノベーターへの変革」、および「社会の期待に応える強靭かつ持続可能な事業活動の強化」を推進します。重要課題とマテリアリティについてはこちらをご覧ください。
サステナビリティ向上につながるアステラスのビジネスモデルであり、「価値」を創造し実現することによって、革新的なヘルスケアソリューションを提供します。 以下の5つのマテリアリティに対する取り組みを推進します。

どのような状況であっても私たちの製品を患者さんに届けるため、事業活動を強化します。以下の4つのマテリアリティに対する取り組みを推進します。

環境のサステナビリティ向上
環境問題に対する積極的な関与が企業に求められています。私たちは,企業活動と地球環境の調和は経営の必須条件であることを強く認識し、地球環境の改善のために主体的に行動しています。上記9つのマテリアリティに加え、以下2つの重要課題に対する取り組みを推進します。

2つの柱に関連する9つのマテリアリティおよび環境に関する重要課題に対し、アステラスが中期的に優先する項目、具体的な取り組み、 2025年度までのコミットメントを策定しました。今後これらのコミットメントに対する進捗状況をアップデートしていきます。
| 最重要課題 | アステラスの中期優先項目 | 具体的な取り組み | 2025年度までのコミットメント |
|---|---|---|---|
保健医療へのアクセス
イノベーション実現のための人材と組織文化
新たなヘルスケアソリューション創出によるアンメットメディカルニーズの充足
革新的な治療手段による根本治療
価値に基づく価格設定 |
研究開発におけるFocus Areaアプローチにより科学の進歩を「価値」に変え、アンメットメディカルニーズの高い疾患の治療のための新しい治療法やモダリティを創出する | アンメットメディカルニーズに応え、従来よりも優れたアウトカムをもたらすソリューションを提供 | 世界の患者さんや介護者の生活を改善し、ヘルスケアシステム全体の負担軽減に貢献する |
|
|
|
|
| 新しいモダリティの革新的な医薬品が世界の患者さんの健康に貢献し、持続可能なヘルスケアシステムを実現していくために、ステークホルダーに向けて価値に基づく価格設定をアドボケートする | 革新的な医療へのアクセスを支える基盤として、価値に基づく価格設定をアドボケート | 価値に基づく価格設定をアドボケートし、ヘルスケアシステムの維持に貢献する | |
|
一人のマネジャーが管理する人数の最適化と階層の削減による組織構造のフラット化、後継者育成の強化、心理的安全性を確保し積極的なフィードバックを促す文化を醸成 | イノベーションを実現するための確かなケイパビリティを持つ人材と組織文化を醸成する |
| 最重要課題 | アステラスの中期優先項目 | 具体的な取り組み | 2025年度までのコミットメント |
|---|---|---|---|
法令遵守と高い倫理観を持った事業活動
製品の品質保証と安全性
責任あるサプライチェーンマネジメント
製品の適正使用 |
予測不能な事態や緊急事態においても製品を継続的に供給する強靭なビジネスを維持する |
|
より持続可能で強靭なバリューチェーンを構築する |
| 製品の品質と安全性を保つためのケイパビリティをさらに高め、患者さんにとっての価値を最大化するために顧客との相互コミュニケーションを最適化する |
|
「品質重視の文化」を醸成し、顧客体験を向上させることによって、製品の品質と安全性を確保する |
| 最重要課題 | アステラスの中期優先項目 | 具体的な取り組み | 2025年度までのコミットメント |
|---|---|---|---|
| 環境負荷の低減 気候変動とエネルギー |
温室効果ガス排出量をパリ協定と整合性のある目標に向け削減し、2050年までに温室効果ガス排出量のネットゼロを達成する | エネルギー効率の向上、太陽光や風力などの再生可能エネルギーへの転換 サプライチェーンにおける温室効果ガスの削減 |
以下目標*に沿った適正な量の温室効果ガス削減を2025年度までに達成する *2030年度までの温室効果ガス排出量削減目標
|
私たちが創出するイノベーションは、社会のサステナビリティ向上の一端を担い、その結果、社会からの信頼を得ることでアステラスのサステナビリティ向上にも繋がると考えています。
企業が社会のサステナビリティ向上に貢献することへの期待は年々高まっています。アステラスは社会からの期待に応えていくことは重要であると考えており、サステナビリティ活動の業績や進捗を適切に開示していきます。
このコミットメントに対してサステナビリティ方針の業績評価指標(SDPIs)を設定し、測定可能かつ適切な具体的アクションを開示することで、サステナビリティ方針を着実に推進していきます。
原則、対象範囲はグローバルとし、冒頭に記載している期間もしくは末日時点での業績を開示
このSDPIsに含まれている医薬品(開発中のものを含む)に関する情報は、宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません:
アステラスは、アンメットメディカルニーズに応えた治療法やモダリティを創出し、世界の患者さんや介護者の生活を改善する優れたアウトカムをもたらすソリューションを提供することで、ヘルスケアシステム全体の負担軽減に貢献します。
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度上期 |
|
|---|---|---|---|---|
| PoC*1を取得したプロジェクト数 | プロジェクト | 0 | 1 | 1 |
| IND*2を取得したプロジェクトの数 | プロジェクト | 4 | 1 | 2 |
| 新規に上市した製品数 | - (Cumulative total since FY2023) | 5 (New: VEOZAH, IZERVAY, VYLOY Additional Indication: XTANDI (M0 CSPC), PADCEV (1L mUC)) | 5 | 5 |
| ブレークスルーセラピー*3指定、ファスト・トラック*4指定、PRIME*5指定、優先審査*6指定、先駆け審査*7指定のいずれかに該当するプロジェクト数 | 件 | 3 | 3 | 1 |
| Rx+新規プログラム数 | プログラム | 1 | 1 | 0 |
*1 PoC:Proof of Concept/コンセプト検証(後期開発への進展の是非を判断するために臨床試験データで効果を確認すること)
*2 IND:Investigational New Drug/新薬の臨床試験開始届
*3 ブレークスルーセラピー:重篤なあるいは命にかかわる疾患に関する薬剤の開発および審査の促進を目的としたアメリカ食品医薬品(FDA)の制度
*4 ファスト・トラック:完治が難しい疾患に対し、高い治療効果が期待できそうな新薬を優先的に審査するアメリカ食品医薬品(FDA)の制度
*5 PRIME:Priority Medicines/欧州医薬品庁(EMA)が実施している、アンメットメディカルニーズを対象とする医薬品の開発支援を強化する制度
*6 優先審査:希少疾病用医薬品の指定を受けた医薬品の他、一定の要件に該当する医薬品について優先的に審査する制度
*7 先駆け審査:有効な治療法がなく命に関わる疾患に対し、革新的医薬品等を世界に先駆けて日本発で早期に実用化するために国内での開発を促進する日本の制度
保健医療へのアクセスは、社会とアステラス双方にとっての最重要課題のひとつです。より多くの患者さんにアステラス製品へのアクセスを提供すること、疾病の認識、予防、ヘルスケアサービスへのアクセスを改善することにより、2025年までに3,600万人以上(累計)にインパクトをもたらします。
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度上期 |
|
|---|---|---|---|---|
| アステラスのコアビジネス(Rx,Rx+) | ||||
| アステラス製品*8を処方された累計患者数 | 人(1994年からの累計) | 1億5,950万以上 | 1億7,400万以上 | 1億7,400万以上 |
| アステラス製品を届けた国の数 | カ国 | 103 | 103 | 103 |
| Rx+ 事業で製品化されたプログラム数 | プログラム | 0 | 1 | 0 |
| アステラス製品の入手可能性の向上 | ||||
| 多様な医薬品アクセスプログラム*9を通じて治療を受けた患者数 | 人 | 2,055以上 | 約11,000 | 約13,000 |
| 多様な医薬品アクセスプログラムの実施国数 | カ国 | 61以上 | 58 | 54 |
| アステラス製品が販売されていない国*10の患者さんに、パートナーとともにアステラス製品へのアクセスを提供した人数 | 人(2023年度からの累計) | 100 | 200以上 | 200以上 |
| 外部パートナーが実施する保健医療へのアクセス向上に向けた活動の協働・支援 | ||||
| アステラスが支援する保健医療へのアクセス向上のプログラムにより影響を受けた人数(2021年度からの累計、財団による支援を除く) | 人(2024年3月時点) | 約31,500 | 約228,000 | 約648,000 |
| アステラス・グローバルヘルス財団による保健医療へのアクセス向上のプログラムにより影響を受けた人数 | 人(2018年度からの累計) | 3,140万以上 | 3,190万以上 | 3,300万以上 |
| アステラス・グローバルヘルス財団の助成金額 | 百万USドル(2018年度からの累計) | 13.3以上 | 13.3以上 | 13.3以上 |
| パートナーと協力し保健医療へのアクセス課題に取り組む研究開発活動の件数 | 件 | 4 | 3 | 3 |
*8 ハルナール、ベシケア、ミラベグロン、プログラフ、XTANDI、XOSPATA、EVRENZO、PADCEV
*9 詳細は以下のウェブサイトをご参照ください
*10 詳細は以下のウェブサイトをご参照ください
アステラスは、価値に基づく価格設定をアドボケートし、持続可能なヘルスケアシステムの維持へ貢献します。
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度上期 |
|
|---|---|---|---|---|
| 価値に基づく価格設定(グローバルでの活動) | ||||
| 価値、アフォーダビリティ、アクセスの課題に対応するため、価値に基づく革新的な価格設定ソリューションが導入された数 | 件(2023年度からの累計) | 5 | 5 | 5 |
| 価値に基づく革新的な価格設定方法によって製品が発売された国の数(累計) | カ国 | 2 | 2 | 2 |
| 価値に基づく革新的な価格設定方法を採用している製品/ブランドの数 | - | 2 | 2 | 2 |
| 価値に基づく価格設定(日本国内における活動) | ||||
| 経団連*12の活動を通じ、価値に基づく価格設定に関して勉強会やイベントでの講演・発表を実施した数 | 件 | 3 | 6 | 3 |
| 価値に基づく価格設定を内容に含む一般市民向けアドボカシー活動の数 | 件 | 8 | 14 | 5 |
*11 一般社団法人日本経済団体連合会
アステラスは、イノベーションを実現するための確かなケイパビリティを持つ人材の確保とイノベーションを促進する組織文化を醸成します。
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度上期 |
|
|---|---|---|---|---|
| サステナビリティ関連イベント実施後にメディアで報道された件数 | 件 | 8 | 7 | 3 |
| 社長からの6階層以下の組織の割合 | % | 83 | 79 | 73 |
| 全組織のスパン・オブ・コントロール *13の平均値 | - | 5.9 | 6 | 6 |
| 社内表彰制度の従業員の利用率 | % | 87 | 92 | 93 |
| 社内表彰制度により表彰を受けた従業員の割合 | % | 76 | 88 | 85 |
| 社内表彰制度の従業員の満足度 | % | 今後測定予定 | 今後測定予定 | 今後測定予定 |
| エンゲージメントスコア | - | 71 | 69 | 73 |
*12 スパン・オブ・コントロール: マネジャー1人が管理する部下の人数
アステラスは、予測不能な事態や緊急事態が生じた場合でも、安全で有効な医薬品を確実に製造し安定的に供給することは極めて重要だと認識しています。製造サプライチェーンやエネルギー調達への事前対策やサステナビリティの観点を盛り込んだサプライヤーの選定を行い、より持続可能で柔軟なバリューチェーンを構築します。
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度上期 | |
|---|---|---|---|---|
| サプライチェーンマネジメント | ||||
| 総電力使用量に占める再生可能エネルギー源による電力の割合 | % | 40 | 39 | 通年データとして開示予定 |
| 非常用電源強化プロジェクトの進捗状況 | - | 国内の製造拠点・研究所に予備電源の導入を実施中または検討中 | 国内の製造拠点・研究所に予備電源の導入を実施中 | 国内の製造拠点・研究所に予備電源の導入を実施中 |
| 地震多発地域の生産サイトにおける耐震補強工事の進捗率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 安定供給のための取り組み | - | サプライヤーとの連携強化に向けた各種取り組みを継続して実施 | サプライヤーとの連携強化に向けた各種取り組みを継続して実施 | サプライヤーとの連携強化に向けた各種取り組みを継続して実施 |
| 地政学的課題に関する代替調達の準備の進捗 | - | - 一部の製品を除く主要製品の代替リソースのリスク評価および準備を完了 - リスク評価中の一部の製品については、代替リソースの特定を完了 - 新製品である Izervay のリスク評価を開始 |
XTANDI: 影響のある原材料に対する代替ソースの特定が完了し、当局の承認取得済み VEOZAH: 代替ソースの特定が終わり、現在薬事手続き中 PADCEV: 二つの代替ソースが確定。一つは使用可能な状態。もう一つは、今年度中の完了を見込む IZERVAY: 代替リソースのリスク評価が完了し、問題ないことが確認済み |
VEOZAH: 主要な薬事対応用の原材料について、代替ソースの適格性評価が完了。現在、規制当局への申請および承認取得が進行中。また、別の原材料に関する代替ソースの適格性評価はFY2026に実施予定 PADCEV: 二つの原材料(ドラッグリンカーの出発原料)の代替ソースについて、適格性評価が完了 |
| サステナブル調達 | ||||
| TPLM*13プログラムの全グループ会社における統一的な運用の進捗状況 | - | 全グループ会社および製造拠点に対し、グローバル化されたTPLMの運用プロセスを導入完了 | - 買収したIveric BioおよびPropella TherapeuticsへTPLMプログラムを導入 - CSRD*14要件に基づき、人権リスクの質問票を更新 - 新しい商品分類コードと契約依頼時に回答する質問をTPLMプロセスに実装 - 新しいABAC*15およびデータセキュリティのデューデリジェンスツールを導入 - 日々の業務サポートをするTPLMヘルプデスクサポートモデルを再構築 - TPRM* 16 (Third Party Risk Management)ベンチマーク分析を完了し、リスクテイクアプローチ、教育・研修フレームワーク、そして包括的なサードパーティリスク監視を確立するための、ロードマップとアクションプランを策定 |
- 質問票の内容、継続的モニタリング、外部データフィード、AIに関連する強化施策の実装を開始 - EHS、ABAC、およびデータプライバシーに関するリスクアセスメント質問票の調整を完了し、質問票へ導入済 - ソルベンシー、労働者の権利、EHSリスクドメインを対象とした新たなモニタリングソリューションの導入も進展中。 - 全社横断型かつ包括的なThird Party Risk管理フレームワークの開発および展開をFY25 第4四半期から開始する予定 |
| サプライヤーエンゲージメント活動へのビジネスパートナー行動規範の組み込み状況 | - | -ビジネスパートナー行動規範をアステラスコーポレートサイトに掲載
-ビジネスパートナー行動規範を「アステラスの持続可能な調達宣言」の一つの柱に含めた -注文書や契約の規約へのビジネスパートナー行動規範の組み込みを実施 |
- 注文書の契約条件にビジネスパートナー行動規範へのアクセス用リンクがない国を特定し修正 |
-ビジネスパートナー行動規範の見直しを実施中 |
| 小規模・多様なサプライヤーに対する年間支出の米国以外の地域への拡大状況 | - | -米国において小規模事業者に約1億3,000万ドルの支出を目標とする「2024 US Small Business Plan」がVeterans Affairs(VA, アメリカ合衆国退役軍人省)より承認を受けた |
- 米国のVAに対し、年間約1億5,500万ドルを中小企業への支出を目標とする2025年度計画を提出。Minority Supplier Development Council (NMSDC)、 National Veteran-Owned Business Association (NaVOBA) や Dun & Bradstreetとのパートナーシップを活用し、実行可能で適格な中小企業の代替案の特定を実施予定 |
-2025年度のSmall Business(SB)実績は VA により承認され、目標を 1億ドル上回る成果を達成 - 2026年度の VA 提出用新計画の策定中。継続してNational Minority Supplier Development Council(NMSDC)、National Veteran-Owned Business Association(NaVOBA)、および Dun & Bradstreet とのパートナーシップを活用し、実行可能かつ適格なSmall Businessの代替案の特定を実施予定 - グローバルでのカバレッジ拡大を目的として、サプライヤー向けポータルシステムの導入についても検討中 |
| アステラス内における「持続可能な調達宣言」の浸透状況 | - | -「アステラスの持続可能な調達宣言」をコーポレートサイトへ掲載 |
- 支出額トップ350の取引先(戦略的/優先的取引先を含む)とのサステナブルビジネスパートナーサミットを開催し、アステラスのマネジメントメンバーが弊社コミットメントと、サステナブルな調達宣言に基づいて設定された目標を達成するために外部パートナーに期待されることを説明 |
-社内イベントのサステナビリティウィークの一環として、組織全体でポスターセッションを実施し、「サステナブル調達宣言」の主要な項目と長期的な目標を社内のステークホルダーに伝達 |
| サプライヤーに取引を発注する際の意思決定プロセスへのサステナビリティ基準の組み込み状況 | - | - 提案依頼書へのESG関連の質問及びガイダンスの組み込みを準備 |
- 取引先契約時の ESG に関する文言の組み込みを検討中 |
- 従業員に対する継続的なトレーニングを実施 - ビジネスを委託する際にサステナビリティ基準を組み込む重要性について継続的に周知・啓発 |
| 戦略的サプライヤーおよび優先サプライヤーに対するSRM*17のガバナンス体系へのサステナビリティの組み込み状況 | - | - 新しいDaaSモジュール(GHG削減を包括的に進めるツール)を既存のSRM(サプライヤー・リレーションシップ・マネジメント)プラットフォームへ取り込む準備を推進中 |
- サステナブルビジネスパートナーサミットの後、アステラスの目標との整合性を確保し、取引先の持続可能性の成熟度を把握し、GHGの一次データの提供を求めるためのアンケートを実施。 |
- 昨年度実施した主要な外部ビジネスパートナー上位350社を対象とするアンケート結果を基に、各社のサステナビリティ成熟度、およびアステラスのサステナビリティ目標に対する理解度、整合性を可視化 -評価結果に基づき、208社の外部ビジネスパートナーを選定し、Scope 3 のCO₂削減達成に向けた詳細なGHG一次データ取得に向けたエンゲージメントを開始 -FY25第2四半期末時点では、一次データ取得率は20%に達し、目標を5%上回って達成 |
*13 TPLM: Third Party Lifecycle Management
*14 CSRD:Corporate Sustainability Reporting Directive
*15 ABAC:Anti-Bribery Anti-Corruption(贈収賄・腐敗行為の防止)。詳細は以下のWebサイトをご覧ください。倫理・コンプライアンス重点エリア
*16TPRM:Third Party Risk Management
*17SRMサプライヤー・リレーションシップ・モデル
*18詳細は以下のウェブサイトをご参照ください
温室効果ガス排出量削減目標を改定しSBT(Science Based Targets)イニシアチブの承認を取得
アステラスは、「品質重視の文化」を醸成し、患者さんのための製品の品質保証と安全性を確保します。
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度上期 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品の品質保証 | ||||
| 様々な社内コミュニケーションチャネルを通じて品質保証の啓発資料を共有する文化の醸成されている | - | CEOを含むトップおよび上級管理職による、品質の重要性に関するメッセージを発信 | CEOを含むトップ、上級管理職および関連する主要部門による、品質の重要性に関するメッセージを発信 | CEOを含むトップ、上級管理職および関連する主要部門による、品質の重要性に関するメッセージを発信 |
| 商用生産施設における品質重視の文化についての評価 | - | 商用生産施設における品質重視の企業文化についてのスコアカード評価を完了し(高岡、富山、高萩、焼津、ダブリン、ケリー、瀋陽)、24年度に重点的に取り組むべき目標課題を特定 | 品質重視の企業文化の共通アンケート設計を完了し、2025年度に取り組む課題を特定 | 現在の質問票の構成について,業界の品質文化フレームワークを活用し、ギャップ評価を実施。 質問票は1つの拠点で試験的な運用を行い、全社展開は現在検討中。 |
| コミュニケーションプラットフォームでリーン・シックスシグマ(Lean Six Sigma) *19の資料とツールが共有されている | - | -リーン・シックスシグマ実践コミュニティが48 か国 より970 名が参加するまでに成長 - 約 100 名のアステラス社員が Lean Six Sigma 認定を取得 - 品質と効率の継続的な改善の実例を共有するライブ・セッションを9 回実施 |
- フィードバックに基づきリーン シックス シグマ ホワイトベルトコースを強化し、アジャイルな業務の進め方に関する資料を追加 |
- 約125名の社員がリーン・シックス・シグマ認定を取得(ホワイトベルト96名、イエローベルト24名、グリーンベルト5名) - リーン・シックス・シグマの活動はローカル単位で進行中 |
*19 リーン・シックスシグマ:品質保証文化を醸成するために、社内において最大限に業務を効率化し、ホワイトスペース(新しいアイデアを模索するために必要なリソース)を創出し、コストを削減するためのアプローチ
アステラスは、パリ協定と整合性のある温室効果ガス排出目標を定め、SBT認証を取得しています。これらに沿って2025年度までに適正な量の温室効果ガス削減目標の達成を目指します。
[2030年度までの温室効果ガス排出量削減目標]*20
スコープ1+2
63%削減(基準年:2015年度)
スコープ3
37.5%削減(基準年:2015年度)
| 単位 | 2023年度 | 2024年度上半期 | 2025年度上期 | |
|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス排出削減率(スコープ1+2) | % | 39.8 | 46.0 | 通年データとして開示予定 |
| 温室効果ガス排出削減率(スコープ3) | % | 18.7 | 7 | 通年データとして開示予定 |
| エネルギー使用量 | MWH | 2,005(TJ) | 494,739 | 通年データとして開示予定 |
| 再生可能エネルギー由来の電力の割合 | % | 40 | 39 | 通年データとして開示予定 |
| 水資源生産性(WRP) | (十億円/千m³) | 0.25 | 0.28 | 通年データとして開示予定 |
| 売上収益当たりの廃棄物発生量 | (トン/十億円) | 8.1 | 6.0 | 通年データとして開示予定 |
| 生物多様性指数 | - | 4.9 | 6.7 | 通年データとして開示予定 |
| 営業車に占める低排出ガス車の割合 | % | 59 | 60 | 通年データとして開示予定 |
| TPLMプログラムを通じて評価されるCMO*21の数 | 件 | 25 | 20 | 通年データとして開示予定 |
アステラスは、ISOのガイドラインISO26000で取り上げられている社会的責任の中核主題や課題について、グローバル基準に基づく管理の有効性を確認しました。ISO26000は、以下の7つの中核主題について慎重に検討する必要性を示しています:組織統治、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者課題、およびコミュニティ参画及び発展。下記のアステラスの取り組みは、このガイドラインに沿ったものです:
グローバル・コンパクトの精神をアステラスのサステナビリティの中で実践
アステラスは、2011年10月に国連の提唱する人権・労働基準・環境・腐敗防止に関する10原則からなる国連グローバル・コンパクトの支持を表明しました。
国連グローバル・コンパクトの署名は、我々の経営理念「先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献する」を実現するために行っているアステラスの活動を裏付けるものです。グローバル・コンパクトの提唱する10原則を日々のオペレーションに組み込み、その取り組み内容を、随時報告書や弊社ホームページ等を通じて報告しています。
国連グローバル・コンパクトとは
1999年にコフィー・アナン氏(当時国連事務総長)がスイスのダボスで開催された世界経済フォーラム(ダボス会議)で提唱した持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みであり、企業が自主的に取り組む原則です。
国連グローバル・コンパクトの10原則
アステラスは、患者さんをはじめとする多様な方々との関わりの中で事業活動を行っています。中でも、患者さんや医療従事者、社員、株主・投資家などへ事業活動が与える影響は大きく、特に重要なステークホルダーと考えています。
アステラスの事業活動を支えるステークホルダーと真摯に向き合い、その期待と要請を理解することは、ステークホルダーからの信頼の獲得と、アステラスの企業価値の持続的向上に必要不可欠です。
そのためアステラスは、さまざまな機会を通じてステークホルダーとコミュニケーションを取っています。また、建設的な対話を促進するために、すべてのステークホルダーに対して適時・適切かつ公平に情報を開示しています。
私たちはこのような情報開示と継続的なコミュニケーションを通じて、企業としての透明性を一層高めていくとともに、社会の持続可能性向上とアステラスの企業価値の持続的向上の実践を目指しています。
| info |
企業経営において、株主にとどまらず、従業員、取引先、顧客、債権者、地域社会をはじめとする多様なステークホルダーとの価値協創が重要になっていることを踏まえ、マルチステークホルダーとの適切な協働に取り組んでまいります。 |
これより先は、アステラス製薬のウェブサイトではなく、外部サイトになります。アステラスは外部サイトのコンテンツやサービスについて一切責任を負いません。
外部サイトへ移動しますか?