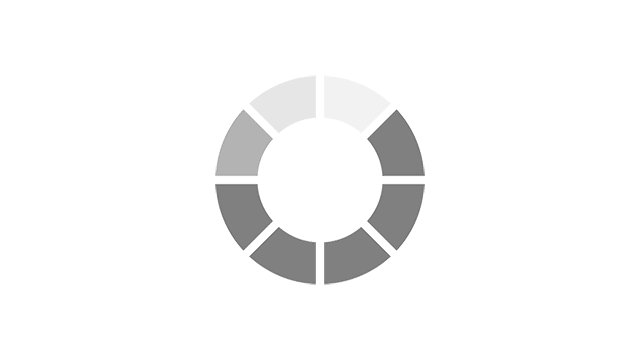
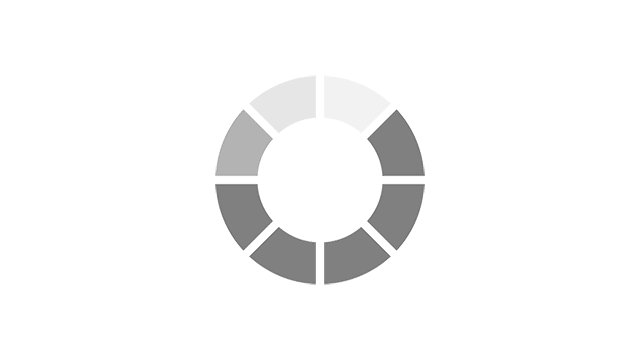
私たちは、できるだけ多くの患者さんにアステラス製品を届け、患者さんの医薬品アクセス改善に取り組みます。私たちは、アンメットメディカルニーズの高い深刻な疾患に対する研究開発活動を通じて、患者さんの「価値」を高めていきます。上記の疾患領域における私たちの治療アプローチは、先駆的かつ複雑であり、診断が困難な場合も多く、また、患者さんの大きなニーズが存在することから、包括的な医薬品アクセスプログラムの提供が強く求められます。
医薬品アクセスを改善するためには製品ライフサイクルの研究初期段階から臨床試験、最終的には治療薬の上市に至るまで、全ての段階において医薬品アクセス改善のための検討を行う必要があります。私たちの製品ライフサイクル全体にわたる医薬品アクセス戦略が、アステラス製品を提供する国、地域にポジティブな影響を与えるよう取り組みます。
臨床試験への登録は、アステラスが開発している治療法に、製造販売が承認される前にアクセスしていただくための最も効果的な方法です。私たちは、患者さんとそのご家族、介護者の負担を少しでも軽減するために、患者さんが臨床試験に参加しやすい環境を整えます。可能な限り、自宅や地域の診療所からより多くの患者さんが治験に参加できるよう、分散化臨床試験を実施します。臨床試験以外のプログラムとして、早期アクセスプログラム*¹や臨床試験後アクセスプログラム*²を実施し、アステラスの治療法へのアクセスを求める、重篤な疾患の患者さんを支援しています。
一部の治療薬については「インターナショナル インポート プログラム(International Import Program)」により、承認取得後、承認取得したその国で、保険償還前の期間に医薬品のアクセスを求める患者さんに対してサポートしています。さらに、特定の製品については「インターナショナル ファーマシー プログラム(International Pharmacy Program)」を通じ、まだ承認取得されていない国で承認取得前のアステラス製品へのアクセスを提供しています。
私たちは、アステラス製品を販売している全ての国において、アステラス製品のアクセス改善に向けた取り組みを実施するために必要な包括的な計画プロセスを有しています。ある国でアステラス製品が販売可能になった後は、その国の患者さんがアステラス製品を入手可能な価格で提供できるよう尽力します。例えば、事前に定めた条件を満たす患者さんが特定の製品を購入する際に治療費を払うのが困難な場合、患者アクセスイニシアチブを通じて経済的支援を提供します。また、特定の疾患領域において、アステラス製品が販売されていない国でも、その製品への医薬品アクセス確保のための方法として医薬品寄付プログラムの実施可能性も検討します。
医薬品アクセス改善は複雑かつ困難な課題であり、ペイシェント・ジャーニー(診断、予防、治療および予後管理を含む医療シーン全般)の各段階において、様々なステークホルダーや医療従事者との連携が必要です。アステラスでは、アステラス製品を必要としている患者さんに確実に届けるために、患者団体や非営利団体、政府機関、アカデミアや他の大手ライフサイエンス企業など複数のパートナーと連携し、グローバルおよびローカルレベルでアステラス製品のアクセスの改善に取り組んでいます。
私たちは、医薬品アクセスの改善が、長期的な健康および社会の持続可能性向上に必要不可欠であると考えています。医薬品アクセスの確保は、経営計画2021の根幹を成す要素の1つであり、トップマネジメントから従業員を含めたアステラス全体を評価する重要な指標となっています。
私たちは日々前進を続けていますが、世界中の患者さんの生活を公平かつより良いものにするために、私たちがやるべき医薬品アクセス改善への取り組みは、まだ多くあると認識しています。私たちは医薬品アクセスを世界中で改善するための方法を探索し続けます。
アステラスは、革新的な治療薬を患者さんへ持続的に提供するため、製品ライフサイクルを通じてアクセスプログラムを実施しています。
医療従事者が患者さんに必要な治療法にアクセスできることは、アステラスにとっての最重要事項です。私たちのリクエスト・プラットフォームを利用することで、医療従事者が患者さんに代わってアステラス製品の提供を依頼することができます。
このリクエスト・プラットフォームは、医療従事者が製品提供の依頼をするための一元的な申請窓口です。アステラス製品へのリクエスト・プラットフォームは こちらをクリックしてください。
アステラスでは「人のために良い事をする」という企業文化が根付いています。その考えの核となるのは、患者さんがどこに住んでいるかに関わらず、私たちの価値判断の中心に患者さんを置くことです。患者さんの医薬品アクセスを改善することで、私たちのVISIONである「科学の進歩を患者さんの価値に変える」を実現できると信じています。
この目標の達成を目指して私たちは歩み続けます。
*1 *2 詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。
https://www.astellas.com/jp/about/policies-and-position-statements?param=expend-tit-medicines#access_to_health
参照
Focus Area アプローチ https://www.astellas.com/jp/innovation/areas-of-interest#focus-area-approach

アステラスはグローバルヘルスと医薬品アクセスの改善に注力しています。2023年度からタンザニアの患者さんに対してプログラフの寄付を実施し、これまでに200名以上の患者さんを支援しました。
ダイレクト・リリーフとの提携により、プログラフはタンザニアで有効に活用され、移植後の健康維持のために免疫抑制療法を必要とする患者を支援することができます。この協働は、持続可能な活動と戦略的パートナーシップを通じてグローバルヘルスにインパクトを与えるという私たちの使命を体現しており、製品のライフサイクルを通じて医薬品へのアクセスを改善するというアステラスの医薬品アクセス戦略に沿った活動です。
アステラスのAtM(Access to Medicines)ステアリングコミッティは、アステラスが事業を展開していない世界中の地域で、持続可能な医薬品アクセスを推進し、健康状態の改善に取り組んでいます。
医薬品アクセスに関する詳細は、こちらの社外ウェブサイトをご覧ください。
ダイレクト・リリーフは、貧困や緊急事態の影響を受けている人々の健康と生活を改善するために活動をしている人道支援団体です。必要不可欠な医療資源を動員し提供することで、ダイレクト・リリーフは最も困難な状況にある人々に健康と希望をもたらすことを目指しています。

Country
Tanzania

主な目標
イノベーションの創出
2021年には全世界で、2億4,700万人以上がマラリアに罹患し、61.9万人の命が失われました。マラリアは深刻な社会課題を引き起こしており、画期的な新薬が待ち望まれています。
アステラスは、外部パートナーとの共同研究を通じて、発展途上国の人々を苦しめる三大感染症のうちマラリアに対する新規治療薬の探索に取り組んでいます。
なお、以下の研究プログラムは、公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金(GHIT Fund : Global Health Innovative Technology Fund)から資金提供を受けて実施しています。プログラムの結果についてはGHIT Fundのウェブページに掲載されています。
マラリア治療薬の探索
アステラスはMedicines for Malaria Venture(MMV)と2017年10月からマラリア治療薬の探索に関する共同研究(スクリーニングによるヒット化合物探索プロジェクト)を行いました。初期プロファイリングにより、スクリーニングコラボレーションで見出したヒット化合物群は、既存のマラリア治療薬と異なる化学構造、作用機序を示す可能性が高く、薬剤耐性マラリアに対する治療への貢献が期待されます。2022年2月より、スクリーニングコラボレーションから得られたヒット化合物群を活用し、薬物動態、薬理活性、安全性を改善したリード化合物を創出することを目指す共同研究契約をMMV、TCG LIFESCIENCE (TCGLS)と締結し引き続き研究に取り組んでいます。

主な目標
イノベーションの創出
顧みられない熱帯病は、主に熱帯・亜熱帯地域の発展途上国の貧困層を中心にまん延している寄生虫、細菌、ウイルス、真菌感染症のことで、世界保健機関(WHO)が焦点を当てている20の疾患群だけでも世界で10億人以上が感染していると言われており、深刻な社会問題になっています。アステラスは、外部パートナーとの共同研究を通じて顧みられない熱帯病の新規治療薬の探索に取り組んでいます。
顧みられない熱帯病創薬ブースターへの参画
アステラスは、2018年3月から顧みられない熱帯病であるリーシュマニア症とシャーガス病のリード化合物*1創出を目的に立ち上げられたコンソーシアム「顧みられない熱帯病創薬ブースター*2」に参画し、本取り組みを通じてリーシュマニア症やシャーガス病に苦しむ患者さんのために新たな治療薬の創出に貢献していきます。このコンソーシアムは、公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金(GHIT Fund)から資金提供を受けています。
*1リード化合物:対象とする疾患に対して薬理活性が確認され、最適化(活性、物性、薬物動態、毒性などを改善すること)研究を行うためのもとになる化合物
*2顧みられない熱帯病創薬ブースター:顧みられない病気の治療薬開発に取り組む非営利組織DNDiが立ち上げたコンソーシアム。アステラスのほか、エーザイ(株)、塩野義製薬(株)、武田薬品工業(株)、AstraZeneca plc、Celgene Corporation、Merck KGaA、AbbVieの7社も製薬パートナーとして参画しています。
シャーガス病に関する新規治療薬の共同研究への助言
アステラスは、2021年11月から2023年9月まで国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)が、非営利組織 Drugs for Neglected Diseases initiative と共に遂行する「シャーガス病治療薬の新規標的としてのオートファジー」について、共同研究のアドバイザーとして参画しています。

アステラスでは、最重要課題である保健医療へのアクセス向上に取り組むための重要なアプローチとして、アステラスの強みと外部パートナーの強みを組み合わせながら、外部パートナーと協働し、活動を支援しています。
このアプローチの一環として、アステラスは、公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金(GHIT Fund:Global Health Innovative Technology Fund)への参画を通じ、結核、マラリア、顧みられない熱帯病など、感染症に対する医薬品、ワクチン、診断薬の研究開発を支援しています。GHIT Fundは、特に貧困国の人々を苦しめている感染症の制圧を目指して、日本政府(外務省、厚生労働省)、民間企業、ビル&メリンダ・ゲイツ財団、英国の財団であるウェルカム、国連開発計画が参画する国際的な官民ファンド(PPP: public-private partnership fund)として、グローバルヘルス研究開発に特化し、感染症と闘ってきました。
GHIT Fundは、この10年間で累積118件のプロジェクトに対して、約291億円の投資を行っています。GHIT Fundの強みであるパートナーシップを活かし、これまでに170を超えるパートナー(国内59機関、海外111機関の製品開発パートナー)が、製品開発に協力しています。(2023年5月31日時点)創薬の初期段階である探索研究から、南米やアフリカにおける臨床試験に至るまで、日本の創薬技術・能力をグローバルヘルスの研究・開発に直接的、かつ効果的に活かしてきました。
アステラスは、第一期から資金拠出をしており、保健医療へのアクセス向上のアプローチに沿って、保健医療へのアクセス課題の解決に貢献するため、GHIT Fundの第三期の活動にパートナーとして継続的に参画します。
関連リンク

公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金

主な目標
イノベーションの創出
命にかかわる感染症「住血吸虫症」
住血吸虫症(別名:ビルハルツ住血吸虫症)*1は、世界で最も蔓延している寄生虫疾患の一つで、78カ国に蔓延し、51カ国で流行しています。また、2億4,000万人以上が罹患しており、公衆衛生上の負担が大きく、経済的な影響をもたらします。貧困との関連性が高く、清潔な水にアクセスできない熱帯、亜熱帯地域において蔓延しています。住血吸虫によって引き起こされる疾患で、人々が生活の中で淡水に触れる際に寄生虫に感染します。小さな幼虫が人間の皮膚から血管に入り込み、臓器を攻撃します。住血吸虫症は慢性疾患であり、子供の感染率が特に高く、世界保健機関(WHO)によって分類される21の顧みられない熱帯病(NTDs)の1つです。
治療をしなければ、貧血、発育不全、学習能力の低下、臓器の慢性炎症を引き起こし、命にかかわることもあります。
住血吸虫症インフォグラフィック
住血吸虫症に対する現在の標準治療は、学齢期や成人の治療に適しています。一方で、小児向けに適した製剤がないために5,000万人の就学前児童が公的な医療プログラムで治療されていないという課題がありました。
小児用プラジカンテルコンソーシアムは、国際的な官民パートナーシップで、住血吸虫症に感染した就学前児童の保健医療アクセスを改善することにより、住血吸虫症という世界的な疾病による苦痛を軽減することを目的としています。生後3カ月から6歳の小児の住血吸虫症を治療するための適切な小児用医薬品を開発、登録、および持続的なアクセスの提供をミッションとしています。
アステラスは、2012年より小児用プラジカンテルコンソーシアムの創設メンバーとして参画し、製薬企業や研究機関、国際非営利組織といったコンソーシアムの参加者とともに、小児に適した製剤の共同開発に取り組んできました。
私たちの革新的な製剤技術は、特に新たな小児用治療選択肢の初期製剤開発において、極めて重要な役割を果たしました。水に溶ける錠剤(150 mg)で、幼い子どもが服用しやすいように苦みを軽減した錠剤を開発しました。
この小児用製剤は、プロトタイプ*2がアステラスにより開発、Merck(本社:ドイツ)により最適化され、高温多湿な熱帯地域においても安定性が高い錠剤を、簡素な製造プロセスでグローバルに製造できるようになりました。
2023年12月、欧州医薬品庁(EMA)の欧州医薬品委員会(CHMP)が就学期前児童における住血吸虫症の新しい治療選択肢に関して肯定的な科学的見解を示しました。新しい治療薬が世界保健機関(WHO)の事前認証や必須リストに登録されるステップに加え、コンソーシアムの実施研究「ADOPT*3プログラム」が進行中であり、アフリカにおいて最初の蔓延国に新たな治療選択肢を導入する準備を行っています。この新たな小児用治療選択肢を必要としている患者さんへ公平に届け、かつ患者さんが将来にわたって利用できるようにする(持続可能なアクセスを確保する)ためには、原料の調達や資金調達の新たな仕組みを共同で模索し、確立する必要があります。
アステラスは、保健医療へのアクセスを最重要課題と捉え、VISION「変化する医療の最先端に立ち、科学の進歩を患者さんの価値に変える」の下、その課題解決に向けて、包括的な取り組みを下記の3つのアプローチで積極的に行っています。
(1) アステラスのコアビジネス(Rx, Rx+)
(2) アステラス製品の入手可能性の向上
(3) 外部パートナーが実施する保健医療へのアクセス向上に向けた活動の協働・支援
コンソーシアムでの活動は(3)に該当し、新たな小児用治療選択肢のEMAによる肯定的な科学的見解は、アステラス製薬が取り組むATH課題の解決に向けた大きな一歩となりました。
アステラスは、今後もコンソーシアムの一員として、コンソーシアムパートナーと連携し、アフリカの住血吸虫症まん延国の子どもたちに製品を届けることができるよう取り組んでいます。
コンソーシアムの活動やパートナーの詳細については、以下をご覧ください。 https://www.pediatricpraziquantelconsortium.org/

新しく開発された小児用製剤
©Merck
*本動画は、GHIT Fundにより2019年7月に作成されました。

アステラスは、新しい知見が次々と明らかになることが医学の急速な発展に繋がっていると認識しています。医薬品の研究開発、医療システムや人的資源のキャパシティ向上に重要な医学知識の発展をアステラスは追求しています。そのため、医学の発展に貢献する医療や科学の研究・教育を支援しています。医療関係者などへの支援は、透明性を確保するため各国のガイドラインに沿って実施されます。
アステラスは、アステラスアカデミックサポートとして、医学・薬学の教育活動への支援を実施しています。具体的には、学会等を主とした医学・薬学に関連する団体の教育事業への財政的支援を対象にしています。
申請概要および申請手続きはこちら
「アステラスアカデミックサポートサイト」に関するお知らせ
株式会社シーエーシー社(以下、シーエーシー社)が提供する寄附金Web申請クラウドサービス「Academic Support Navi」(以下、当サービス)につきまして 、2025年12月25日よりシステム障害の影響によりサービスが停止されております。
詳細につきましては、以下シーエーシー社のニュースサイトにて、最新情報をご確認ください。
ニュース| 株式会社シーエーシー(CAC)
これに伴い、弊社「アステラスアカデミックサポートサイト」からも、当サービスへアクセスいただけない状況となっております。
ご利用の皆さまには多大なご不便とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます 。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
アステラスアカデミックサポートに関するお問い合わせは、以下事務局メールアドレスまでご連絡ください。
academic-support@mail.acsprtnavi.c-nuage.jp
アステラスは、医学・生命科学の活動の発展への貢献を目的に、高い透明性・公正性を確保しつつ、アカデミアによる研究活動を継続的に支援しています。
研究活動支援の一環として、2019年度まで奨学寄附を実施してまいりました。しかしながら、製薬企業から医療関係者への資金提供に関し、世界的な共通認識として、より高い透明性と公正性を担保し、説明責任を果たすことが求められている中、奨学寄附という形態で医療関係者に直接支援することは、法令および業界ルールに則っているとはいえ、ステークホルダーより疑念を抱かれる可能性を排除できないと判断し、アステラス製薬は2020年3月をもって奨学寄附を終了致しました。
2020年度からは、より一層高い透明性・公正性を担保しながら研究活動支援を継続するため、従来実施してきたアステラス病態代謝研究会(AFRMD : Astellas Foundation for Research on Metabolic Disorders)への支援を強化しました。AFRMDはアステラスとは独立した団体であり、アステラスは助成対象の選考に関与していません。
アステラス病態代謝研究会は、1969年に設立され、生命科学研究、とりわけ創薬・治療法の開発・実用化研究を奨励し、国民の保健と医療の発展及び治療薬剤の進歩に貢献することを目的に活動しています。同財団は、次の時代を切り開く研究テーマへの研究助成、卓越した若手人材の発掘・育成・海外派遣のサポートを通じて、わが国の医学・生命科学に貢献しています。
研究助成では、「独創性、先駆性が高い萌芽的研究提案」あるいは「臨床的意義の高い成果が期待できる研究提案」を支援しており、また、以下の研究者を特に応援する等、先進的な支援を行っています。
2024年度の研究助成金は、1,155名の応募の中から80名の研究者に、1億6,000万円が交付されました。海外留学補助金は、202名の応募に対し、11名の研究者へ総額 5,566万円が交付されました。
また、2022年度からは、次世代人材の育成、画期的な創薬・治療法の開発・実用化ならびに新たな研究領域の創出のため、新たな取り組み「AFRMD Next-generation Innovators’ Challenge (ANIC)」が開始されました。ANICでは、これまでの研究助成採択枠を増やすとともに、海外留学補助金を増額、さらに、将来的にイノベーションを巻き起こすようなユニークな研究の継続的なサポートを強化するためステップアップ研究助成が行われております。2024年度のステップアップ研究助成では、59名の応募に対し、10名の研究者に総額4,000万円が交付されました。

アステラスは「先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献する」を存在意義として事業活動を行っています。革新的な医療ソリューションを研究・開発し、患者さんへ届けることにより、保健医療へのアクセス(Access to Health)の向上に注力しています。一方で、患者さん個々を取り巻く環境は異なり、この中には医療では解決できない問題も数多く存在しています。私たちは、薬づくりという事業活動とともに社会貢献活動も重要な企業活動であると考えており、患者さん・患者さん家族への支援として患者会支援(スターライトパートナー)活動を行っています。
スターライトパートナー活動基本方針
スターライトパートナー活動では下記のような支援を提供し、患者団体の自立、持続的な発展をサポートしています。

「患者会支援(スターライトパートナー活動)申請サイト」に関するお知らせ
株式会社シーエーシー社(以下、シーエーシー社)が提供する寄附金Web申請クラウドサービス「Academic Support Navi」(以下、当サービス)につきまして、2025年12月25日よりシステム障害の影響によりサービスが停止されております。
詳細につきましては、以下シーエーシー社のニュースサイトにて、最新情報をご確認ください。
ニュース| 株式会社シーエーシー(CAC)
これに伴い、弊社「患者会支援(スターライトパートナー活動)申請サイト」からも、当サービスへアクセスいただけない状況となっております。
ご利用の皆さまには多大なご不便とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
患者会支援(スターライトパートナー活動)申請サイトに関するお問い合わせは、以下お問い合わせフォームよりご連絡ください。
スターライトパートナー活動 お問い合わせフォーム
2024年度
| プログラム名 | コンテンツ | 参加団体数 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| ペイシェントエキスパートプログラム | 次世代リーダー向け研修:医療環境の理解とディベートスキルを習得するための研修 | 5 | 5 |
| リーダーシップ・トレーニング・プログラム | 次世代リーダー向け研修:組織運営のためのマネジメントスキルとリーダーシップコミュニケーションを習得するための研修 | 14 | 21 |
| ピア・サポート研修 | 患者さんや患者さん家族向けの研修:ピアサポートの理論、コミュニケーションや傾聴のスキルを習得するための研修 | 24 | 29 |
アステラスは、患者団体が実施する活動やイベント(社会への疾患啓発の促進や、患者さん自らが自身の疾患について深く学ぶ取り組みなど)に対し、助成金を通じて支援しています。
2024年度
| 団体数 | 総額(円) |
|---|---|
| 9 | 4,716,300 |
アステラスは助成金活動終了後に助成金報告会を開催しています。助成金で取り組んだ活動の成果を振り返るだけではなく、他団体の活動事例や取り組みにおける工夫やノウハウを学べるよき交流機会となっています。
また、アステラスの社員もオブザーバーとして参加し、患者団体の具体的な活動内容や患者さんたちが抱えている課題などを学ぶよい機会となっています。
2024年度(2024年度は該当団体なし。2025年度は実施予定)
| 団体数 | 総額(円) |
|---|---|
| 0 | 0 |
アステラスは、患者団体自らが企画・主催する「ピアサポート研修会」の実現を支援します。アステラスがピア・サポート研修の講師を派遣し、「講師謝礼」「講師交通費」「講師宿泊代」を全額負担します。
2024年度
| 派遣された講師が所属する団体数 | 参加者数 |
|---|---|
| 2 | 37 |
ピア・サポート研修講師派遣の申請概要と申請手続きはこちら
アステラスは、患者団体が主催するイベントに対し、イベント資材を無償で提供しています。
2024年度
| 団体数 | 提供した資料の総数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボールペン | プラスチックフォルダー | ノート | 紙袋 | 名札 | |
| 17 | 1030 | 70 | 470 | 680 | 240 |

医薬品アクセスインデックス*(Access to Medicine Index、以下ATMI)は、医薬品アクセス財団(Access to Medicine Foundation, 以下ATMF)が、世界の大手製薬企業20社を対象に、低・中所得国における医薬品アクセス向上の取り組みを「研究開発」、「製品供給」、「医薬品アクセスに対するガバナンス」の3領域において2年ごとに評価し、報告書として公表しています。アステラスは2010年からATMIの調査に回答しています。
2024年のATMIでは、アステラスは15位となり、2022年の16位から順位を上げました。アステラスは「医薬品アクセスに対するガバナンス」の領域で高い評価を得ています。背景として、特に、医薬品アクセス戦略を策定したことがあげられます。製品の入手可能性をさらに向上させるためには、製品のライフサイクル全般において、包括的で統一された戦略が必要だと認識しています。部門横断での議論により、「Access to Medicine Playbook」をまとめ、医薬品アクセス戦略を実行しています。一方で、キャパシティ・ビルディング(「製品供給と研究開発」の一部)が改善余地のある項目として特定されています。
アステラスが注力する包括的な保健医療へのアクセス向上の取り組みは、外部パートナーと協力して医療に関するケイパビリティや技術を発展させ、そして世界中の患者さんに医薬品を届けるというATMFの目標につながっています。
ATMI報告書の評価項目には、倫理感と責任感を持った事業活動、保健医療システムの強化、製品の品質保証とサプライチェーンマネジメントなどが含まれており、これらはアステラスにおける最重要課題でもあります。最先端の「価値」駆動型ライフサイエンス・イノベーターへの変革と、社会の期待に応える強靭かつ持続可能な事業活動の強化によって、全社一丸となってサステナビリティへのコミットメントをより強固なものにしています。
これより先は、アステラス製薬のウェブサイトではなく、外部サイトになります。アステラスは外部サイトのコンテンツやサービスについて一切責任を負いません。
外部サイトへ移動しますか?